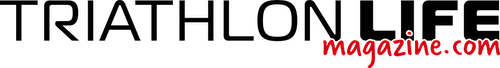2020年のツール・ド・フランスにて想いに耽ったこと。
考えてみると社会人になってからずっとスポーツに携わる仕事を筆者はやってきている。いや小学校の野球に始まり中学時のサッカー(マラドーナ世代です)、その後陸上競技と子どものころかららスポーツが日常にあった。その過程の中でいくつか、激しく心が揺さぶられる、背中を雷に打たれたような衝撃を受けた瞬間がある。
たとえばオリンピック。2004年のアテネ(トライスロン)、2008年の北京(競泳)に取材に行ったときや、2002年の日韓ワールドカップを生で観戦したとき。あのときはドイツ✕アイルランド戦が最も印象に残っていて、アイルランドのロビー・キーンが同点ゴールを決めたときのスタジオが揺れる地響きのような歓声に鳥肌が立った。
そしてツール・ド・フランス。
世界3大スポーツはオリンピック、ワールドカップサッカー、そしてツール・ド・フランスといわれている。最近では昨今の盛り上がりもあってか、五輪、W杯サッカー、ワールドカップラグビーと称する人もいるようだが、我々の世代は断然ツール・ド・フランスだ。
それをこの目で確かめたかったことが、そもそもツールを追った理由のひとつでもあったのだが、とにかく予測をはるかに上回る圧倒の連続だった。
ツールをほかの2大イベントと比べ、フランス国内(とその周辺国)だけのレースじゃないか、と指摘する向きもいるかもしれない。しかし競技人口は本場ヨーロッパはもとよりアジア、オセアニア、北米、中南米、そしてアフリカとサッカーと同じく5大陸に渡っている。
その中のトップ中のトップがフランスに集まり最高峰を目指すレース、つまり「The top of the cycle road races. The top of the cyclists」なのである。

そんなレースでは観客にも目を奪われる。
老若男女、乳母車に乗せられた子どもからお爺ちゃん、お婆ちゃんまで、一瞬で通り過ぎるライダーたちを心待ちにし、3時間以上も前から沿道に陣取るのはあたり前。勝負どころとなるピレネーやアルプスでは、数日前からキャンピングカーで寝泊まりする多数のグループがいるというのは有名な話だ。
そして、選手が通過する前に訪れるキャラバン隊が振る舞うスポンサーグッズやお菓子、そして一番人気であろう水玉Tシャツやサイクルキャップを子どもに混じり大人も我が先にと無邪気に拾う姿に、ちょっと日本人にはない文化だなとも感じる。
そりゃそうだ。100年以上の歴史をもつレースの中で、彼ら大人たちも幼少時に自分の親に連れられてレースを見ていたのだから。いわば物心がつく前から自転車が身近にあり、身体に染みついているスポーツといえるのだろう。

ああ、何か筆が止まらなくなってきた。
強引なたとえになるが、野球では筆者はタイガースファンだ。コロナ禍になる前までは年に1、2回は甲子園に足を運んでいるが、そこには何と表現していいのか。独特の味を出している観客や、思わず笑けてしまうオッチャン、オバチャンなどが東京の球場と比べても圧倒的に多くいる。
そして、ここでも目につくのが子どもの姿だ。生粋のトラ吉オッサンに連れられてきているのだろう。ある意味、英才教育といえるが、それはスポーツのあるべき姿として間違ってはいないと思うのだ。彼ら、彼女らは一生涯阪神タイガースを背負っていくのであろう。
話を戻そう。
そんな筆者の経験の中でひとつ、絶対に忘れられないレースがある。それが95年のハワイだ。
一般的にハワイというとオアフ島の観光地をイメージするのだろうが、我々のハワイというのはハワイ島・コナで行われるアイアンマンのことを指す。
今から25年前、まだ当時のトライアスロン雑誌の編集部1年目で競技の何たるかも知らない状況の中、目の当たりにしたハワイ。今思えばちょっと段階を飛び越し過ぎていたような気もするが、まさに子どもが、理屈を越えたとてつもないパワーをもった競技に魅了されたようなものだった。そして、大げさにいうとこの先、本気でスポーツを生業にし続けていこうと決意したレースでもあった。
その地に来年、15年ぶりに行く。さてどんな感情が湧いてくるのだろうか。
<文/ TRIATHLON LIFE 編集部>
>> アイアンマン世界選手権2022(ハワイ)の特集ページ
>> アイアンマン世界選手権2021(セントジョージ)の特集ページ ※リンク